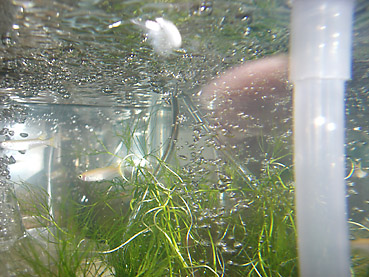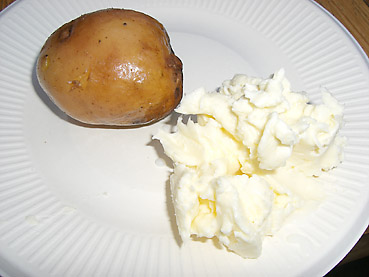豪快!うまい!の趣あふれる石焼き料理
北海道の国立日高青少年自然の家で行われた、アウトドアクッキングキャンプで、料理講師を務めさせていただきました。
そのときのサプライズ料理が、この石焼き料理です。
石焼き料理とは、秋田県の男鹿の漁師の暮らしの中から生まれた、磯の香り漂う豪快な郷土料理です。
木のオケに、魚介類を入れ真っ赤に焼けた石を放り込むというもの。
ジューっと、瞬時に煮あがるために、魚介類の身が引き締まり、プリプリとした食管が楽しめます。
見た目の演出としても豪快で、そのうまさはもう絶品。
本来料理に使う石は男鹿半島でも貴少な入道崎の火成岩「金石(かないし)」を使用しますが、なかなか手に入りそうもないので、今回は、 ホームセンターで手軽に入手可能な敷き石に使う御影石のブロックを使用してみました。
<石焼き料理>
所要時間 約40分
材料費 約1500円(6人前)
<用意するもの>
炭コンロ 1台
木炭
敷き石用の御影石 2個
<食材>
お好みの魚介類
(今回は、鮭、エビ、アサリ)
長ネギ
だしの素
みそ
使用後の写真ですみませんが、これが今回使用した御影石です。ホームセンターで1個48円で購入しました。 玄関のアプローチなどに使用する敷き石です。焼き石料理には、 火山性の石を使用しないと加熱したときに割れてしまいますのでこの御影石はおすすめです。
まずは、木炭を真っ赤に燃やして、御影石をその中に入れて真っ赤に焼けるまでじっくりと焼きます。
お好みの魚介類を用意します。
だしが出るようにエビやアサリを入れてみました。
秋の北海道では、鮭が旬なので入れてみました。
本来は、鯛やソイなどを入れると良いそうです。
我が家の家庭菜園で栽培した有機無農薬の長ネギも入れ、粉末のだしを加えます。
石が焼けて本当に真っ赤になってきます。
その石を火バサミでつかみ、灰を吹き飛ばして鍋に入れます。
入れた瞬間にジュワッと音がします。
この分量で、石を2個入れます。
10秒ぐらいでもうぐつぐつと煮立ってきました。
材料に火が通ったところで、みそを加えて出来上がりです。
秋のホームパーティーに、見た目も温かい石焼き料理はいかがでしょうか?身体が温まりますよ!